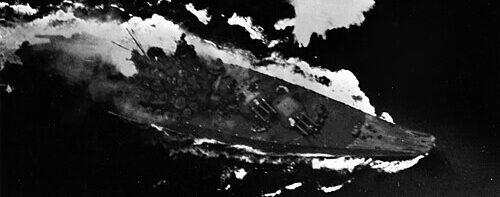1. 大東亜戦争――私たちは何を失い、何を植え付けられたのか
今回は大東亜戦争と、その後の日本の歩みについてお話しします。
でも、ただの歴史講義ではありません。
なぜ私たちが今もなお、自分の国の歴史を自分の言葉で語れないのか――
なぜ学校で学んだ歴史と、事実として残っている史料との間に、こんなにも大きな隔たりがあるのか――
その理由を、一緒にたどっていきましょう。
1. 戦後レジーム――見えない檻
「戦後レジーム」という言葉を耳にされたことがあるでしょうか。
これは単に戦後の政治体制や憲法体制を指すだけではありません。
もっと深く、もっと静かに――私たちの心の奥底にまで入り込み、価値観や誇りを覆い尽くしてしまった見えない檻のことです。
昭和20年、8月15日。日本はポツダム宣言を受諾し、敗戦を迎えました。
そこから昭和27年のサンフランシスコ講和条約発効まで、実に7年間、日本は連合国軍の占領下に置かれます。
その中心となったのが、GHQ――連合国軍最高司令官総司令部です。
彼らは軍事的支配だけでなく、日本人の精神そのものを変えることを目的としました。
なぜか、それは大東亜戦争を通して日本人があまりに強かったため、二度と戦いたくない、ずっとこの先隷属状態に置いておこうと考えたからです。
2. WGIP――戦争への罪悪感を植え付ける
占領軍が用いた心理的作戦が、ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム(War Guilt Information Program)、略してWGIPです。
直訳すれば「戦争罪悪感情報計画」。
もっと端的に言えば、「日本人に戦争への罪悪感を刻み込むための情報操作」です。
内容は非常にわかりやすいものでした。
「日本軍国主義は悪であり、国民はその犠牲者である」
「原爆投下はアメリカ兵の命を救うためのやむを得ない手段だった」
「日本は残虐な行為をしたのだから、深く反省しなければならない」
こうしたメッセージを、新聞、ラジオ、学校教育を通じて、何度も何度も繰り返す。
やがて、人々はそれを事実として受け止めるようになっていきます。
「時が熱狂と偏見とをやわらげた暁には、また理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には、その時こそ正義の女神はその秤(はかり)を平衡(へいこう)に保ちながら、過去の賞罰の多くにそのところを変えることを要求するであろう」
ラダ・ビノード・パール東京裁判インド代表判事
パール判事は、極東国際軍事裁判(東京裁判)が最初から日本を侵略国と決め付けていることに不快感を示した。そしてこの裁判の本質は、連合国側の政治目的を達成するために設置されたに過ぎず、日本の敗戦を被告達の侵略行為によるものと裁く事によって、日本大衆を心理的に支配しようとしていると批判した。
さらに、検察側の掲げる日本の侵略行為の傍証を、歴史の偽造だとまで断言した。
かつて欧米諸国がアジア諸国に対して行った行為こそ、まさに侵略そのものであると訴え、全被告を無罪だと主張した。

3. 驚くべき事実――贖罪意識はなかった
ここで、ひとつ驚くべき事実があります。
敗戦直後の日本人の多くは、今日の私たちが抱いているような加害者意識や贖罪感を持っていませんでした。
戦争の痛みはもちろんありました。
空襲の被害、家族や家を失った悲しみ。それは計り知れません。
しかし「自分たちが悪だった」という意識はほとんどなかったのです。
では、なぜ今のような自虐的な歴史観が広まったのか。
それは占領軍が直接「こう考えろ」と命じたのではなく、日本政府や日本の報道機関を通して間接的に思想を流し込んだからです。
これが実に巧妙でした。
外から押し付けられたと感じなければ、人はその考えを自分のものとして受け入れてしまう。
そして、その思想はやがて常識となり、次の世代に受け継がれていくのです。
4. プレスコード――沈黙を強いる鎖
ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム(WGIP)を支えるもうひとつの柱が、「プレスコード」です。
これはGHQが占領期に制定した報道統制の規則で、日本中の情報発信を厳しく制限しました。
新聞、雑誌、ラジオはもちろん、民間人の手紙までが検閲されました。
毎月およそ400万通もの郵便物が開封され、内容をチェックされたといいます。
電報や電話も盗聴されていました。
さらに、GHQや連合国を批判する記事、大東亜共栄圏を肯定する文章、戦争犯罪人を擁護する発言などはすべて禁止。
禁止事項は30項目もあり、GHQに不利な内容を一切封じました。
以下に主なものを挙げます。
• SCAP(連合国軍最高司令官もしくは総司令部)に対する批判
• 極東国際軍事裁判批判
• GHQが日本国憲法を起草したことの言及と成立での役割の批判(注:2018年4月26日修正、原文に基づく)
• 検閲制度への言及
• アメリカ合衆国への批判
• ロシア(ソ連邦)への批判
• 英国への批判
• 朝鮮人への批判
• 中国への批判
• その他の連合国への批判
• 連合国一般への批判(国を特定しなくとも)
• 満州における日本人取り扱いについての批判
• 連合国の戦前の政策に対する批判
• 第三次世界大戦への言及
• 冷戦に関する言及
• 戦争擁護の宣伝
• 神国日本の宣伝
• 軍国主義の宣伝
• ナショナリズムの宣伝
• 大東亜共栄圏の宣伝
• その他の宣伝
• 戦争犯罪人の正当化および擁護
• 占領軍兵士と日本女性との交渉
• 闇市の状況
• 占領軍軍隊に対する批判
• 飢餓の誇張
• 暴力と不穏の行動の煽動
• 虚偽の報道
• GHQまたは地方軍政部に対する不適切な言及
• 解禁されていない報道の公表
そして、焚書(ふんしょ)。
7,000冊以上の本が発禁処分となり、図書館や書店から姿を消しました。
これらには、戦前の日本の立場や大東亜戦争の意義を説明する本も含まれていました。
抵抗すれば、警察力が行使されます。
こうして、日本人が自分の国の歴史を客観的に学べる資料は、ほとんど奪われてしまったのです。
5. 自虐史観の固定化と現代
こうして占領期に作られた歴史観は、戦後教育によって固定化されました。
戦前の日本を肯定的に語ることはタブーとなり、「軍国主義による侵略と破滅」という一本の筋書きだけが教科書に載りました。
戦後教育を受けた世代が社会の指導層となっても、その枠組みは変わらず引き継がれました。
学校、学会、マスコミ――その多くが占領期の価値観を、今もなお手放していません。
そして私たちも、その価値観の中で育ち、知らず知らずのうちにそれを自分のものとしてしまっているのです。
6. 占領政策の本当の恐ろしさ
ここで考えてみてください。
占領軍はなぜ、ここまで徹底的に日本人の精神を変えようとしたのでしょうか。
答えは簡単です。
武力で相手を支配しても、その力が去れば元に戻ってしまう。
しかし、価値観や歴史認識を変えてしまえば、その影響は世代を超えて続く――。
これこそが、占領政策の本当の恐ろしさです。
「日月神示」にみる占領政策
- 「悪の仕組は、日本魂をネコソギ抜いて了(しま)ふて、日本を外国同様にしておいて、一呑みにする計画であるぞ。日本の臣民、悪の計画通りになりて、尻の毛まで抜かれてゐても、まだキづかんか」(磐戸の巻第十帖)
- 「日本の上に立つ者に外国の教え伝えて外国魂に致したのは今に始まったことではないぞ。」(梅の巻第十一帖)
- 「神の国は結構な国で、世界の真中の国であるから、悪の神が日本を取りて末代までの棲み家とする計画でトコトンの知恵出して、どんなことしても取るつもりでいよいよを始めているのざから、よほど褌締めて下されよ。」(地つ巻第十帖)